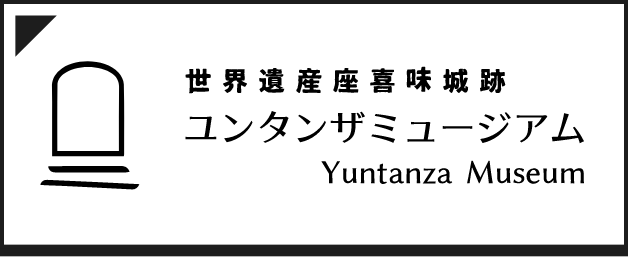第19回沖縄タイムス賞 「自治賞」に輝く読谷村の概要(その1)
読谷村のあゆみ
戦争前の読谷村は、農家率九五パーセントという純農村だった。農産物の品種改良についての研究も盛んで、明治から昭和の初期にかけて県の奨励品種であったイモの「佐久川種」やサトウキビの「読谷山種」の発祥地でもある。
戦時中、主要農耕地が旧日本軍の飛行場用地に接収されたのに引続き、戦後も米軍基地として使用され、一時は村の全面積の八〇パーセントが基地に占められていた。その後、徐々に開放されているが、現在でも六六パーセントが基地である。
沖縄戦で米軍の上陸目標地点にされた読谷村は、激しい空襲と艦砲射撃に見舞われ、村民は国頭村に集団疎開、戦後は中北部の収容所に収容された。
昭和二十年八月十五日、日本がポツダム宣言を受諾して戦争に終止符が打たれると、中北部の収容所にいた人たちは、それぞれの村への移動を許されたが、飛行場をはじめ米軍基地の多い読谷村民は村への移動を許されなかった。
昭和二十一年四月には、ほとんどの住民が旧市町村に移り住み、米軍によって市町村長が任命された。読谷村も、知花英康氏が村長に任命されたが、村役所は胡差に置くという変則的な形で戦後の村政のスタートを切ることになった。
各地に分散する村民の強い要請で、村長は米軍や当時の民政府と折衝、昭和二十一年八月、ようやく波平と高志保の一部が開放され、これに伴い村長は、六百人の「建設隊」を編成して、新しい村落の再建にのり出した。
建設隊は「協力して村再建に挺身し、理想郷を建設する」という主旨の建設剛領のもとに、総務、建築、農耕、衛生、食糧の五つの部を設け、それぞれ業務を分担して宅地の造成、規格住宅の建築、農耕などにとりかかった。一方、各収容所には「建設後援会」が組織され、建設隊に対する金、物品、労力などの協力計画を立てて協力するとともに移動の準備を整えた。
受け入れ準備が完了すると、建設隊本部で前村会議員を中心とする第一回村政委員会を開いて、村民移動の方法、それに伴う役所、学校、配給所など公共施設の用地選定などを協議するとともに、村名を「読谷山」から「読谷」に改め、心機一転して新しい村づくりにあたる決意をした。
村民の移動は、十一月二十日から開始、十二月十二日には約五千人が郷里に帰り、第一次移動を完了した。同時に、各字毎に代表を置き、これを中心とする自治機関を設け、村の建設方針、計画を協議、これを村民に徹底させる方法をとった。ここで誕生した新しい自治機構がずっと引きつがれ、今日の新しいコミュニティーとして部落の自治制度に発展している。
当時、基地と隣接する住民地区では、米兵と住民との間にトラブルが絶えなかった。だが、読谷では、字単位に設けた自治機能が十分機能、トラブルがなかった。その実績が認められ、他の部落も次々と開放になった。
そのつど「建設隊」が活動して村づくりが行なわれ、1号線(現在の国道58号)の東側と一部を除いて開放が進み、昭和二十二年十一月の第四次移動で村民の郷里への復帰は完了、一万四千人が再び村内に定住した。
だが、戦争が終わって三十年を越えた今日、また六六パーセントの土地が基地に接収され、昔の部落に帰れず、建設隊によって割り当てられた土地に居住を余儀なくされている部落が、二十二部落中十指を数えている。