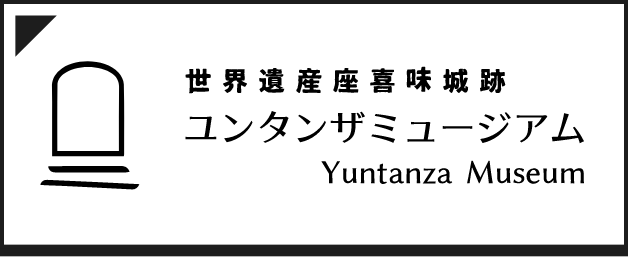読谷山の文化財 №2 読谷山間切の焼物
厨子甕は、死んだ人の遺骨を、火葬はしないで洗骨をして丸ごと納めておく、大きな甕である。これは墓の中に安置されるので、前の大戦でも破壊をまぬがれて、現在でも沢山残っている。その中に、その甕をやいた年代や、それを焼いた地名をはっきり刻みつけた非常に珍らしいのが現在一つだけ発見されている。それによると、この甕は今から約三〇〇年前、わが読谷山間切で焼かれたこと、そして入っていた遺骨の主は、今の那覇市安謝の、上地大主夫人であったことがわかる。すなわち読谷では、あの当時から遠い安謝辺りからも注文をうける程の、りっぱな焼物を作っていたことになる。しかし残念ながら、その後のことはよくわかっていない。戦後になって、沖縄考古学界の長老多和田真淳氏によって、その窯跡が喜名部落の西外れで発見された。それで今では、昔の読谷山の焼物を、喜名焼といっている。沖縄の焼物は、大ざっぱに、上焼と荒焼にわけることかできる。上焼とは、たっぷり釉をかけて焼き上げたもので、今の読谷壷屋焼はこれにあたる。焼物とは、ふつう釉をかけずに固く焼き締めたもの
で、喜名焼はこれに入る。喜名焼の特徴については、いろいろの意見があるが、ここでは分り易いものとして、県立博物館学芸員、ヤチムン会員の宮城篤正氏の説をお借りして、かかげておく。「喜名窯から採集した陶片からその特徴をあげると、まず陶片の素地土中に含まれている鉄分やアルカリおよびアルカリ土類の成分によって自己施釉の状態になっていることと、陶片の断面をみると、赤褐色部と黒褐色部の二層に分かれ、壷や甕の表側になっている黒褐色部の表面は薄く施釉した状態でもある。焼成は還元焔によったとみられ、表面側の鉄分が黒褐色に変化しているので、おそらく焼成温度は一二八○度前後と考えられよう。」
※写真は原本参照