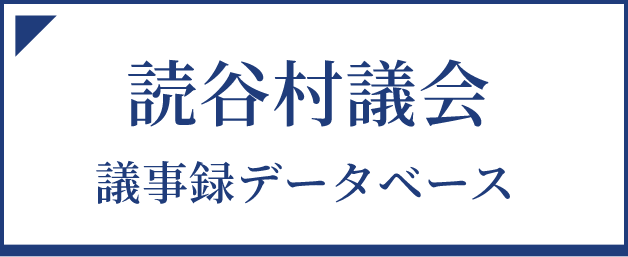まちづくりの基本は、民主的な地方自治の確立と住民参加による地域活性化にあるという立場から、自治労は住民生活に直結した施策をするために一九八八年、全国の十カ所のモデル地域(市町村)を指定しました。
そのモデル地域に沖縄県では本村(読谷村職員労働組合)が指定を受け、以来、地域活性化運動に積極的に取り組みを始めました。
運動には、商工会や農協、漁協、婦人会、青年会、老人クラブ等の村内緒団体との協力体制の下に、①一九八九年「ユンタンザぐすくフォーラム」、②一九九〇年「語やびらユンタンザニ〇一〇年」、③一九九一年「ユッカヌヒー残波玩具まつり」のイベントを実践。また、米人家庭を宿泊施設に転換した「Pハウスゆめあ~る」を設置するなど、モデル単組としてのむらおこし事業を展開。その活動は自治労中央本部を始め、県内外から高い評価を得ています。
そのような中、自治労の地域活性化モデル単組に指定され、独自の活動を展開してきた全国(北海道から九州)の十単組が本村に集い、十一月六日~九日の日程で「自治労地域活性化モデル単組読谷集会」を開催。むらづくりの情報を交換すると共に相互の交流が深められた。
七日午後に行なわれた集会には、活発にむらおこし事業を推進し、内外の注目をあびている商工会の西平朝吉事務局長を講師に招き「読谷の地域づくりを進めて」を演題として基調講演。西平事務局長は、琉球の歴史や読谷村のアイデンティティー、国際化時代に向けてのビジョンや商工会のむらおこし事業などの経過について触れ「地域を活性化するには、地元の物を掘り起こすことが重要」と説き「地域の人達が文化と解け合う読谷村は団結力のある地域。村民一丸となって進み、協力体制がとれるメリットがある。昭和五十九年に商工会は地域ビジョンを策定し、翌年に推進委員会を結成。昭和六十一年から具体的なむらづくり運動に着手し、婦人の生活改善グループによって紅いも菓子やメロン、スイカの漬物などの特産品を開発してきた。しかし、販路開拓が課題になり紅芋菓子を製造するポルシェのルートを活用して県内のスーパーなどに少しづつ商品を出品してきた」と販路開拓の難しさを述べ、更に「紅いも菓子が売れるようになったのは紅いもシンポジウムを催してから、紅いもが接点となり行政、農家、加工業者が一つにまとまり、村民の特産品という考え方に変わってきた。地域づくりには人、物、金が必要。行政の協力を得て、村民が一緒になれる横の連携をつくることが大切です」と強調して、講演を終えました。(八日には山内村長の「読谷村のムラづくり」と題しての講演を開催)
本土の集会参加者(二十二人)らは、読谷のムラづくりのノウハウを学びつつも、両日にわたって『読谷まつり』を見学。勇壮・華麗でスケールの大きい読谷まつりに全員が感動。舞台ステージでのカチャーシーに参加して踊り、進貢船に乗船するなどして読谷まつりを楽しみ、素晴らしい感動の思い出を胸にそれぞれの帰路の途につきました。